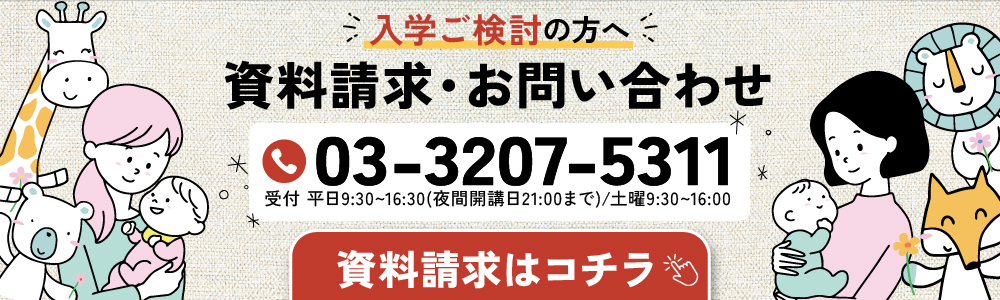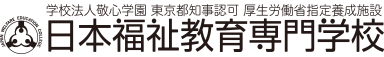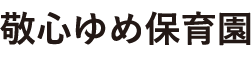ニュース
きのしたひろこの「不思議シリーズ」vol.3~「歌うこと」の不思議~ 専任講師(音楽担当) きのしたひろこ
2025年2月04日 9:00
♪せんせいおはよう、みなさんおはよう~♪今日も通り沿いの保育園から元気な声が聞こえてきます。調理室からは早々と換気扇からいい匂いも漂い、スーパーへ買い物に出かける途上の私は思わずうれしくなってニコニコしながらリズムに合わせて歩きます。不審者⁉
私は本校保育福祉科夜間コースの担任をしていますので、午前中に家族の夕食の準備を整えてから出勤するのが日課なのです。
さて、「歌うこと」の不思議のついて考えてみたいと思います。幼保の現場ではなぜ、まず朝に、みんなで一緒に歌うのでしょう。私たちが発する声は、単純に言えば空気を振動させて耳に届く「音」の一種ですね。スズメもカラスも、猫も犬も、私たち人間も、いろいろな情報を声で仲間に伝えています。私たちが原始人だったころ(笑)、仲間と力を合わせ狩りをして食べ物を獲得する、収穫を分け合う、という社会生活の中で、声を合わせて歌うことは連帯と協働のための大事な方途でした。お母さんお父さん、家族や保育者の力を借りながら社会の中で育ち、生きていく私たち人間は、生まれながらに「歌う」ことを必要とする生き物である、と言えるでしょう。
2020年9月放送のNHK『チコちゃんに叱られる』では、「なんで歌うとストレス解消になるのか?」というテーマが取り上げられていました。チコちゃんの答えは「人は歌うと幸せになるいきものだから~。」でした。確かに、先生の伴奏に合わせてみんなで歌うことが毎日のルーティーンとなることで、「歌うぞ!」という気持ちの準備が朝の会では自然に促されます。そして一定のビートに合わせてみんなでのびのびと歌うことで、副交感神経が刺激され、リラックス状態になり、深い呼吸が促されます。さらに先生やみんなの顔を見ながら表情筋や舌筋を使って歌い合うことで、先に述べた原始時代の遺伝子レベルに組み込まれた喜怒哀楽を歌と共に乗り越えてきた太古の記憶が脳内に蘇るのです。一緒に歌うことで、「ここにいれば大丈夫。さあ今日も仲間と、先生と一緒に楽しむぞ!」との主体的な一日の出発が促されます。保育者も心を開き、子どもたちの心や様子を感じ取りながら歌い合うことで一緒に保育実践のスタートを切ります。この「歌うこと」のヒト遺伝子に組み込まれた不思議については、さらにまた続編にて♡
じぶんに会ったクラスを選べる
オープンキャンパスはこちら